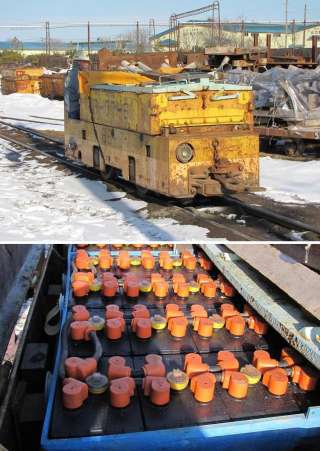2011年01月26日 17時59分

昨年の10月25日以来の「ケーブルカー」話し。
今回は、「六甲ケーブル」です。
正式な会社名は『六甲摩耶鉄道』と言い、
路線名が「六甲ケーブル線」です。
「六甲ケーブル下」~「六甲山上」間、1.7キロを
10分で結んでいます。
この線には平成15年12月14日に乗っており、
写真は、「六甲山上」発16:30、
「六甲ケーブル下」着16:40の乗車時に撮影しました。
写真は、2編成ある内の「クラシックタイプ」の車両で
“フェスティバルカラー”と呼ばれる緑と赤の塗り分けが美しく、
私はもう一編成の「レトロタイプ」よりこちらの編成の色の方が
好きです。(どうでも良いことですが…)
(概要)
高低差…493.3メートル。
最急勾配…26度。
軌間…1067ミリ。
この写真では良く分からないと思いますが、
このケーブルの架線は2本あり…、
と、ここまでは分かっていたのですが
今回、「六甲ケーブル」の公式HPを見ていて驚きの発見!
それぞれ、片方がAC(交流)200ボルト「電灯線」、
もう片方がDC(直流)100ボルト「信号線」の文字が???
何せ私は文系で、技術的なことは“サッパリ”なのですが
一体どういう構造になっているのでしょう?