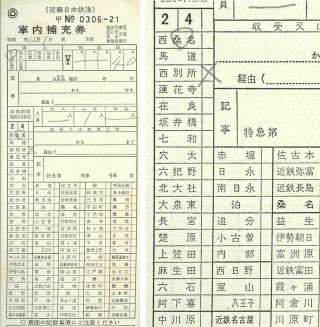2011年02月23日 18時43分

平成14年当時の冊子にあった地名の「クランダ」の記載ですが、
この列車の公式HP(日本語版)では「キュランダ」となっているので、
今はその冊子も「キュランダ」になっているかなと思いつつ…。
さて、列車は『バロンフォール』で観光停車します。
“フォール”というだけあり、
バロン「滝」の絶景を楽しむ“駅”なのですが、
写真は、『何両位の客車が繋がっているのか?』ということを
実感してもらうために掲載しました。
矢印のところの機関車からグネグネと客車が
多分、10両は繋がっていたのではないでしょうか?
※正確な編成両数を数えていませんでした。申し訳ありません。
この『バロンフォール』の周辺の緑が濃いことが見て取れますが、
既に列車は熱帯雨林の中を走っていたはず。
(記憶が怪しくてすいません。今一、確証が…)
“人生、山あり谷あり”とよく言いますが、
この鉄道は、山あり、谷あり、滝あり、熱帯雨林ありと
盛り沢山な内容となっており、
「ケアンズ駅」から暫くの間の平原も含めその景色は飽きることなく、
さすがに「ケアンズ観光」の目玉だけあると実感しました。
●客車もレトロで車内も雰囲気があってGOODです。
座席はボックスシートですが、山側に通路があり、
谷側(絶景サイド)に4+4の8人がけの配置で、
まるで、仕切りの無いコンパートメントみたいな感じでした。
もともとそういう座席配置なのか、それともこの列車用の配置なのかは
不明です。