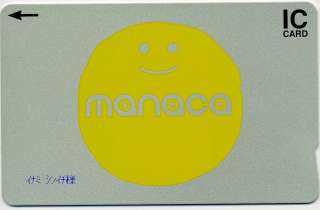2011年02月13日 18時13分

「賢島駅」に定刻11:25到着予定が結局10分ほどの遅れ。
●写真は、何年かぶりでの「賢島駅」でパチリ。
近鉄のHPに書いてあった
『伊勢志摩の豊かな太陽光線にちなんだ・・・』というこの電車の説明や、
指定席券にもある「太陽」のシンボルマークが
これほど恨めしく思えたことはありませんでした。
ところで、今回乗車した「名古屋」~「賢島」間の
『伊勢志摩ライナー』のスジは、23000系誕生前からあるものですが
様変わりもしています。
今、昭和55年(1980年)10月号の時刻表を見ているのですが、
その当時だけではなく、多分、10年ちょっと前までは
1時間に1本、宇治山田までのノンストップ(甲)特急がありました。
伊勢志摩方面への取材時の往復は、余程のことがない限り
その甲特急の時間になるべく合わせて行動していたはずです。
それが今や、平日の運転は無くなり、土・休日だけの運転で
しかも「津駅」にも停車するようになりました。
※今回の同行者に『「津駅」は以前通過していた』と話したら
驚かれました。
所要時間は2時間4分からこの電車の場合でジャスト2時間と
少し速くなりましたが、今は昔の思い出ですね。
ここまで書いていて不思議な感覚に捕らわれました。
伊勢志摩方面の取材は、多い時で1年に4~5回以上あったはずで、
それなのに平成6年登場のこの電車との出会いがなかったのは何故?