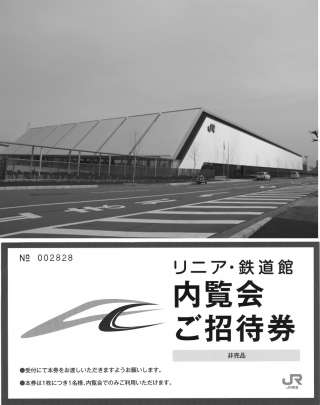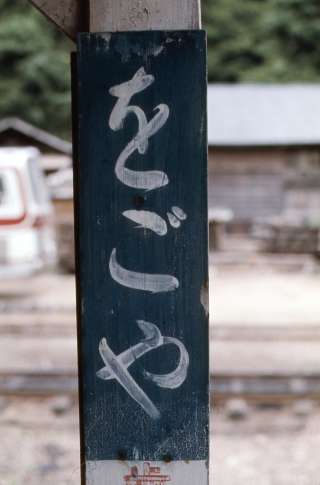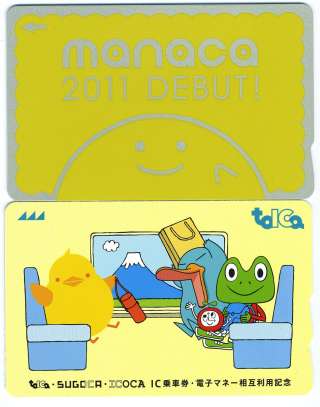2011年03月10日 0時00分

こちらは『超伝導リニアシアター』です。
(今回は「アーカイブ」の話しはしません)
上の写真が外観で、下がその内部です。
正直言って、侮っていました。
JR東海「リニア・鉄道館」の皆様には失礼な話しで恐縮ですが、
実は、単に“映像”を見せる『ブース』だと思いこんでいたのです。
ところがどっこい!
車内は、本物のリニアと同じ造りになっていて、
椅子をリクライニングさせてゆったり座っているだけでもリニアに
乗った気分になれ、山梨リニア実験線の試乗会の抽選に
落ち続けていた私にとっては、これだけでも達成感があり、
気分は上々でした。
で、いざ走り始めると・・・。
テーマパークのライド系で、椅子が動くアトラクションを
想像してください。
車輪走行から浮上走行、そして再度の車輪走行まで、
その微妙な振動や揺れが、椅子を通じて体に伝わってくるのです。
勿論、正面スクリーンや横にある窓外を流れるCGの風景の
迫力もあるとは思いますが、リニアがどんな“乗り物”であるかを
知るには十分でした。
正直、『超伝導リニアシアター』の情報があまり出てこないのが
意外な位で、多分、「山梨実験線での試乗」との違いは、
車体や風景などが本物かどうかだけであり、
それを問わなければ限りなく実車に近いのでは想像しています。
「リニア・鉄道館」で唯一、「リニア」を実感できる施設ですので、
私の隠れ一押しと言っても過言ではありません。