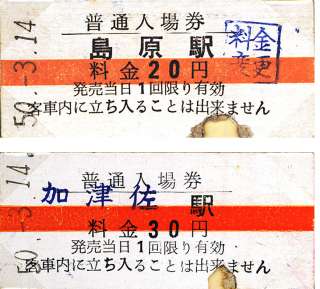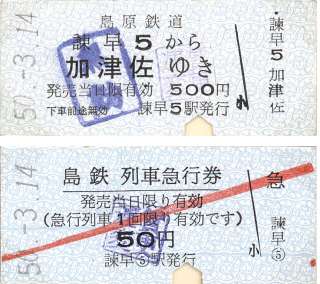2011年05月21日 19時35分

「島原外港駅」は、「Wikipedia」によれば平成9年に交換設備が
撤去されており、平成20年までは有人駅だったようです。
また、「島原外港駅」が今もあるのは島原市の“要望”とありました。
『やはりそうなんだ』と改めて感じました。
その「島原外港駅」から「加津佐」方面には、写真のようにまだ
線路が残されています。本線とも繋がっており、線路の撤去費用の捻出が
きっと出来ないのだろうと思い、ついでに言うと、この先、踏み切りの
あったところはどうなっているのだろうと心配になってしまいました。
その理由ですか?それは、車で「踏切」を横断する場合、本来
『一時停止』義務があるのですが、廃止となった「踏切」にはその義務が
ありません。ところが「踏切」がそのままの姿で残されていた場合、
“廃止”を知っていようがいまいが、無意識で一時停止してしまいそうです。
その時、後続の車に「一時停止」する気が無ければ、追突されるのでは
などと心配になってしまったのです。
話しは脱線しても、列車を脱線させてはいけません。
この写真は、列車の車内から撮影したものですが、この駅で折り返さず、
このまま「加津佐」方面にそのまま走り出しそうな感覚に囚われました。
既に3年の月日が流れているとはとても思えない「島原“夢幻”鉄道」の
巻でした。