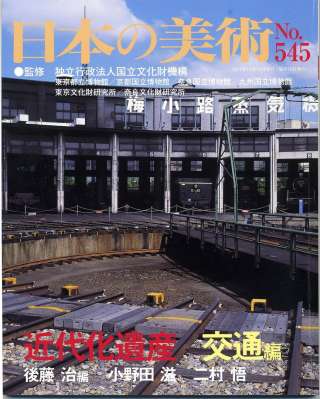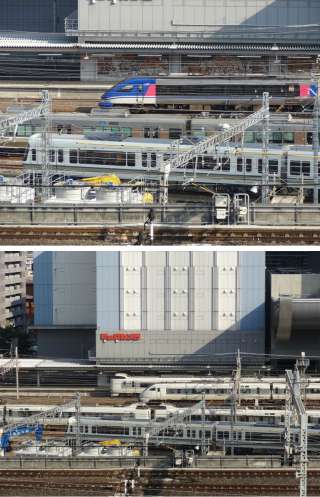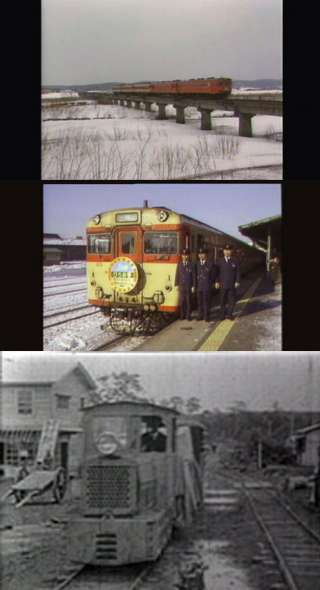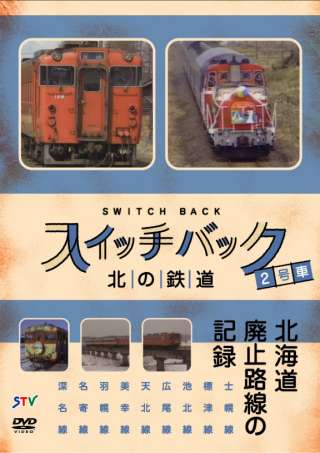2011年10月21日 18時30分

「帯広の郊外に鉄道の資料館を個人でやっている人がいる」とは
昨年の2月に初めて知ったのですが、その時『館長』の穂積さんに
「必ず伺います。その時はよろしくお願いします。」と約束し、
空手形になることなく今回訪問が実現しました。
穂積さんによると、最近は『何故か観光バスの団体が来ることもある』
この「小さな鉄道博物館」だそうですが、まずは玄関を一歩入って
いきなり「鉄」のカウンターパンチを食らいます。
左側の写真がそうですが、玄関を入った真正面の2階にある“博物館”に向かう
階段の取っ掛かりのところで、写真では分かりにくいですが真ん中の上に
あるのは廃線となった「北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線本別駅」の
運賃表です。そして階段にピッタリな『橋をお渡り下さい』の看板も
“博物館”の雰囲気を盛り上げてくれます。
右側の写真は、階段を上り始めて右に進路をとったところですが、
今度は左側に「ふるさと銀河線本別駅」「ふるさと銀河線塩幌駅」で
掲示されていた発車時刻表があり、正に『おもちゃ箱をひっくり返した
ような』とはこの“博物館”のためにあるといっても過言ではないと
思ったほどです。
でもここはまだまだ序の口で、幕内には到達していません。
(観光バスの件)
最近は『こだわり』のあるツアーが人気のようで、『2429Dの旅』でも
8時間の普通列車がツアーコースになっていることに驚かされましたが、
この「小さな鉄道博物館」に観光バスが来る時代になっているとは
更に驚かされました。
因みにその時のツアー参加者は中高年の女性中心だったそうで、
“博物館”は10人も入れば見学困難なほどの狭さゆえ、
順番に入ってもらったそうです。