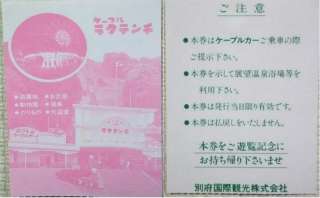2011年01月29日 17時38分

『まやビューライン夢散歩』摩耶ケーブルの終点「虹の駅」から
「摩耶ロープウェー」を乗り継ぎ到着した
「星の駅」下車直ぐ目の前ある
摩耶山掬星台(きくせいだい)からの眺望です。
昼間でもこれだけの絶景ですが、
「手で星を掬(すく)える」という名前の由来の場所だけに
「100万ドル」ならぬ「1000万ドル」の夜景の名所だそうで
観光客もさることながら
市民にとっても昼は遠足、夜(?)はデートの名所であったりで、
“思い出”の多い場所のようです。
話しは脱線しますが、私は「高い所」から「下」を
眺めるのが好きで、戦国時代に武将たちが高い山の上に
お城を構えたのは、単に『守り』のためだったとは思えません。
(見当違い?)
子供達が小さかった頃は私が率先して大観覧車に乗ったり
飛行機だけではなく熱気球なども乗ったことがあります。
また、「鉄道の絶景ポイント」を問われた時には
「篠ノ井線の姨捨」「肥薩線の矢岳越え」を真っ先に挙げるほどで
私だけではなく、多くの方達の賛同は得られると思っています。
また高い所から“広い景色”を眺める観光地は日本だけではなく
世界中にあります。
さて話しがどう繋がっていくかと言うと
昨年の11月8日に、「函館山の夜景」の話しを書いていますが
乗客はとても多く、ロープウェイも最新式のものでした。
ここ「掬星台」からの夜景を、私は写真でしか見ていないのですが
それが『函館の夜景』に大きく見劣りするとは思えません。
勿論、乗り継ぎが必要で、一本で展望台に行けないと言う不利は
ありますが、観光地としての「神戸」の地位は低くは無いはず。
それだけに夜景(絶景)ポイントとしての「掬星台」が
世間にもっと知られ
「摩耶ケーブル」に明るい兆しが見えてくることを
既に手遅れの感が無きにしもあらずですが改めて願うものです。