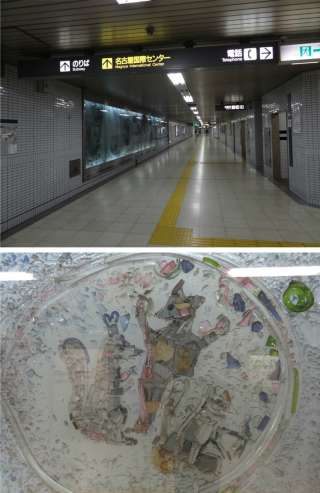2012年05月05日 18時20分

高山本線の「富山」~「猪谷」間を普通列車に乗ったのは私が記憶する限り、初めてのことで、最初に乗ったのは昭和46年(1971年)8月17日で、急行「北アルプス」号でした。その後も特急「ひだ」で通過したことはありますが、“普通列車”の良さは流石にノンビリと風景が楽しめ、窓からゆったりした気分で写真も撮影できることです。
上段写真は、米どころ富山平野の春らしい風景。田植えを前にして水をはったのでしょうか、水面が鏡のようになり、家々を映していました。
またその向こうには山々が聳えて(そびえて)いるのですが、ガスっていてあまりはっきりは見えません。
高山本線の旅の魅力は、何と言っても風景の素晴らしさにあります。海には縁がありませんが、平野から山に分け入り、その山が作る渓谷美も半端な存在ではなく、最後にまた平野に戻っていく如何にも『山国日本』を感じさせてくれるのが私が高ポイントを付ける理由です。
そんなことを考えていたら「笹津」駅に到着。私の眼の前に如何にも古めかしい駅名標が飛び込んできました。JR西日本の定番ではなく、こんな駅名標も残されているんですね。こんな発見も“普通列車の旅”ならではでないでしょうか?それにしてもこの駅名標は昭和4年(1929年)の開業時の名残ということもあり得るのでしょうか?