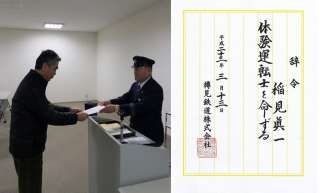2011年04月04日 8時50分

上段の写真は、主幹制御器のモデルです。
何でこんなものがあるかというと、“学科講習”の最後に、
このモデルを使って主幹制御器(マスコン)の操作を実習しました。
まあ考えてみれば、まず『運転』の第一歩がマスコンであることは
間違いなそそうです。
しかし、こうした体験は“お初”でした。
画面のないトレインシミュレータと言った所でしょうか?
そして、下段の写真ですが、私に運転の順番が回ってまいりました。
マスコン・ブレーキ弁ハンドルを持つ手も様になって…いる訳ないですね。
●手袋は参加費の中に入っていますが、帽子は運転時に貸してもらいます。
そして指導運転士さんが、参加者運転中の写真を撮ってくださいます。
それにしても自分で言うのも何ですが、
なぜもっと嬉しそうな顔が出来なかったのでしょう?
でも、「楽しもう」「楽しもう」と思えば思うほど何故か体が硬く
なってしまうのです。
ところでノッチには5段階があるのですが、
段階ごとにクリックされるわけではないので、
ノッチとノッチの途中のところで止めてしまうことがあります。
そうするとフルノッチの状態となる時があり、
その途端「大きな警告音」がなります。
参加者でその「警告音」を鳴らさなかったのはほんの数名です。
さて私は???ご想像にお任せします。
これは「そういうシステムになっている」からなのだそうですが、
そもそも何でこんなややこしい構造になっているかについては
聞きそびれました。
なお、この「運転体験」では“3ノッチ”までしか使いません。