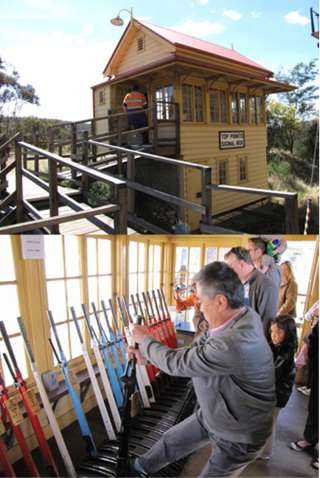2013年08月14日 18時57分
これが今回宿泊した「Hotel Villa Sommer」。12室というこじんまりしたホテルで、何と有線LANが使え、快適にインターネットが繋がりました。
このホテルを選んだ理由は、バート・ドーベランの駅前と言う立地。一昨日にUPしたモリー鉄道の走る市街地にもホテルはあるのですが、そこまでトランクを持って移動するのを嫌いここにしました。勿論、部屋から列車が見えるであろうとは期待していました。
(グーグルマップの航空写真で確認。そう言えば(1)の列車交換も「Bad Doberan, Deutschland」で検索するとその様子が見てとれます)
実際に出かけてみて分かったことは、車で移動している人ならともかく私のように公共交通機関で移動している人間がバート・ドーベランの市街地に泊まろうとすると、結局1時間に1本のモリー鉄道を使うことになり、それはそれで楽しいのですが、今回の選択は良かったと思います。前にも書いたのですがこのホテルと市街地が徒歩10分弱という近さにあります。またその間にスーパーもあったりして買い物もできます。
そして泊まった部屋はトレインビュー。いつもの見下ろしではなく見上げるトレインビューに泊まるのは初めての経験でした。
※ネットで予約しています。勿論日本語サイトです。ただ予約確認の紙はドイツ語表記のモノ持参が必須です。それにしても便利な時代ですね。
※このホテルに入るにはインターフォンでスタッフを呼び出すところからスタートです。パリで同様のホテルに泊まっていたのであせることは無かったのですが、なんだか慣れることはありません。パリとの違いはホテルの出入り口の『鍵』。パリは毎回インターフォンでの呼び出しでしたが、ここでは部屋の鍵で解錠が出来るようになっていました。所変われば品変わる。
昨日に続いて「旅」写真をご容赦ください。
「ドイツ人はイチゴ好き」とは聞いていました(過去形は冗談です。今回の旅の感想です)が、街中にイチゴの立ち売りスタンドがありました。こうした立ち売りは他の街でもあったのですが、こんな可愛いスタンドはここでしか見かけませんでした。因みにこのスタンドの右側に駐車する車の列が見えますが、その更に右側のモリー鉄道の線路があります。今思えば工夫次第で込みの写真が撮影できたかもしれません。そうそう、この写真は許可を得て撮影しています。
さあっ、明日からは鉄分の放出をします。