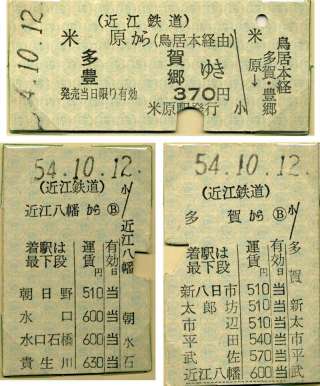2011年10月17日 18時05分
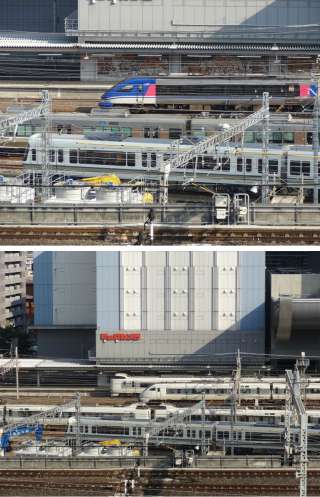
上段写真の撮影時間は8:32で、下段写真が8:40です。
上段・下段とも一番手前は「クハ221-24」で、奈良線の朝の
ラッシュ運用を終えて、側線でしばしの休憩(?)といったところでしょう。
次に上段写真の一番奥は、智頭急行HOT7000系で、
画面左側から右側に走っています。
ということは折り返し「スーパーはくと3号」(京都発~鳥取行き)と
思われ、その京都発は8:52なのでそのために京都総合運転所から
回送での入線でしょう。
その手前は恐らく京都発18:31の新快速姫路行き。
下段写真の一番奥は京都駅8:36に到着した「きのさき4号・
まいづる2号」(福知山・東舞鶴発京都行き)の新鋭287系。
その手前は京都発8:41の「サンダーバード5号」(和倉温泉行き)。
更にその手前はサンダーバード4号(金沢始発)と思われ、
京都駅発は8:37ですので少々遅れているようです。
何も考えずにただボーっと眺めているだけで、どんどん時間が
経っていきますが、取りあえず8:45に部屋を出て、この日の仕事先に向かいました。