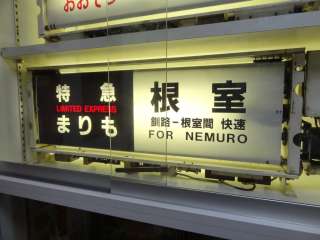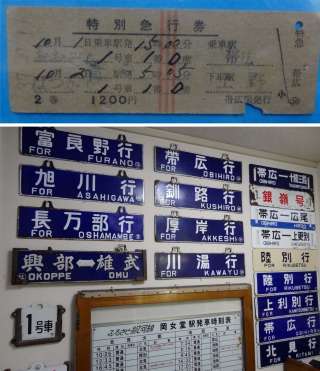2011年12月04日 17時28分

昔、「紙ふうせん」というデュオが『冬が来る前に』と言う歌を
歌っていたのを思い出しました。
「冬が来る前に」と思いつつもう全国的に冬ですね。でも8月の
小樽に“もう一度めぐり逢いたい”と今、こうして書いています。多分、このブログを読んで下さっている殆どの方には通じない
歌の話しですね。(反省)
今年は2度北海道に渡っており、1度目は7月9日から14日の三笠鉄道村等への「鉄」旅(このブログでは7月28日~10月26日の間でUP)で、2度目は8月24日から28日までで、こちらは会社の出張でした。
その初日の24日に少し時間が取れたので「小樽市総合博物館」に
出かけました。
で、まず向かったのは旧手宮線です。この線への探訪は結構マニアックかと思いきや、何と小樽市の観光ルートの一つになっており、
駅に併設の観光案内所で「旧手宮線マップ」(旧手宮線沿いにある観光名所を紹介している)なるものを手に入れ、早速向かいました。
と言ってもメインの「小樽市総合博物館」の滞在時間の問題もあり、
小樽駅前から海岸へ向かう『中央通』と『旧手宮線』のクロスする場所を
確認しただけに留まりました。
(小樽駅からそこまでは徒歩で5分も掛かりません)
右側の写真は、そのクロスポイント、中央通の中央分離帯に設置された
モニュメントで、車輪(動輪)には「TEMIYA LINE」と
刻まれており、道路を横断した左側には「旧手宮線」の解説板が
設置されていました。
また左側の写真ですが、道路を横断した先から「南小樽」方面を
臨んだもので、遊歩道として整備されているのが見て取れます。写真でのお分かりいただけるようになかなか雰囲気が良く、多くの
観光客や地元の方も歩かれており、人のいない写真を撮るには
意外と時間が掛かってしまいました。
私は「小樽市総合博物館」の入館時間を計算し、結局ここからタクシーに乗ってしまったのですが、時間が許せば「散歩しながら行くのも良いだろう」と思いました。