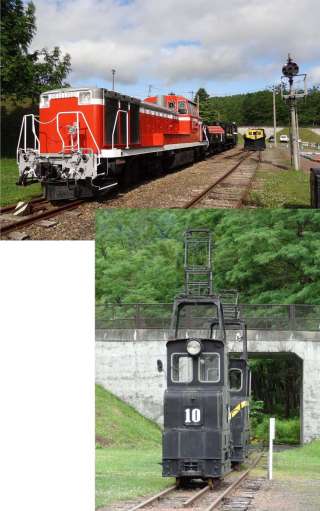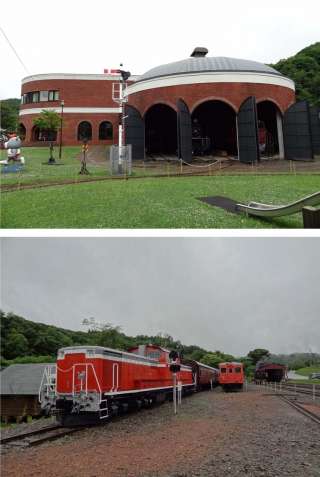2011年08月01日 8時00分

平成23年7月10日(日)、三笠鉄道記念館で何となく
撮っていた一枚です。
まあ建物の前で目立っていたのは間違いありませんが…。
この動輪の物語は、『SL機関士体験クラブ』の「運転体験」時の
指導機関士さんから聞きました。
まさに「人に歴史あり、動輪に物語あり」を実感したので
ここに紹介させていただきます。
※指導機関士さんは元国鉄~JR北海道勤務で、蒸気機関車を
実際に運転されていたそうです。
『D51603』は、国鉄で最後に工場での検査を受けた
蒸気機関車とのことで、最終的には北海道・追分機関区の所属でした。
ここからは『Wikipedia』「D51」の情報も少し加味しますが、
国鉄最後の蒸気機関車の機関区がその追分機関区で、
昭和50年12月24日に、国鉄蒸気機関車の“本線”走行の
歴史が閉じました。
その後、廃車となった『D51603』は、東京・上野の
「国立科学博物館」に保存される日を待っていたのですが、
昭和51年4月13日深夜、追分機関区の扇形庫が炎上し、
この機関車も後ろ半分が焼け落ち、その結果、機関車の前半分が
JR西日本・嵯峨野線「嵯峨野駅」前にあり『嵯峨野観光鉄道』が運営する
『19th CENTURY HALL(「トロッコ嵯峨駅19世紀ホール」が
分かりやすいかな?)』に、そして動輪がここ三笠鉄道記念館に
やってきたそうです。
指導機関士さん曰く、追分機関区の火災には驚くとともに
新製配置のDD51とともに焼け落ちた蒸気機関車群の姿には愕然とした
そうです。
※嵯峨野観光鉄道に保存されている「D51603」の前半分の写真には動輪が2対見えるので、この動輪は第3動輪と思われます。
今思えば、動輪の“刻印”を確認すれば良かったと思っています。
ただの展示物かと思いきや、紆余曲折を経てここにいるというのが、
何か不思議な感じがしました。
では次回から、『SL機関士体験クラブ』の話しをUPします。