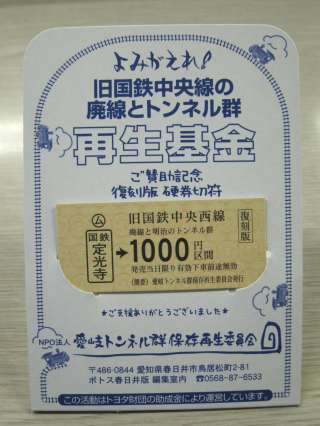2010年11月17日 9時00分

恥ずかしながら、乗車直後の私です。
他のお客さんがたまたま近くにいなかったので
こうして悠然と乗っています。
もしも、この博物館に多数の入場者がいて
周りに家族連れがいた場合を考えると
私の年齢で、しかも一人で来て
如何にもこの炭鉱トロッコ列車に乗るが目的ですとばかりに
この“人車”に乗り込み、記念写真まで撮るのは
勇気が必要そうです。
「北海道鉄道博物館」と「炭鉱トロッコ列車」の
2つの纏めですが、
ビルの6階という決して条件の良くない場所に
『よくぞ作ったもんだ』に尽きます。
また、函館駅のど真ん前という立地は賞賛に値します。
特に「トロッコ列車」は、「博物館」と違い
『モノ』を持ち込んで展示方法を
工夫すればよいという訳ではなく、
線路を敷き、そこを『安全に走らせないといけない』訳で
あくまでも私・個人の意見ですが
「ここに作る」ことを決めた決断にまずは拍手。
多分に“遊び心”からの発想とは思いますが
上手くここが「函館」の新名所に育ってほしいと
名古屋から祈っています。
(余談)
話しが飛びますが、カラマツトレインが運営する
北海道三笠市の「三笠トロッコ鉄道」に
行ってみたくなりました。
ただ子供が小さかった頃に一緒に行けていたなら
どんなに楽しかったであろうと思いつつ…。