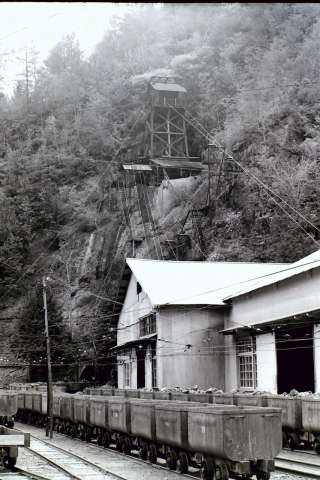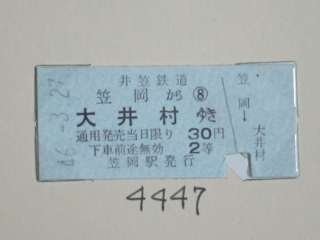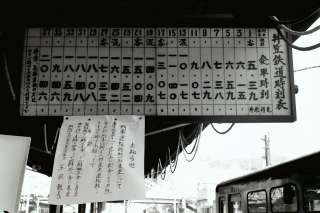2010年05月16日 19時15分

珍しく(?)仕事中の私です。
この写真は、同行の取材スタッフが撮影してくれました。
注目してほしいのは取材用カメラです。
今時、民生用はデジタルカメラが当たり前で
記録媒体がDVDやHDD、メモリーカードという時代ですが、
昭和50年代前半の取材と言えば「フィルム」の時代。
使っているカメラは西ドイツ製(当時は東西分裂の時代)の
『アリフレックス』。
フィルムサイズは16ミリ。
タングステン光用ポジフィルムを日常的に使っており
屋外ではASA100を選択。
何故か、テレビの現場ではデイライト用の
フィルムはあまり使いませんでした。
このため色調整に「フィルターワーク」を要求され、
当然の事ながら「自動絞り」ということもあり得ず、
更にフィルムの交換は、ダークバッグにカメラを入れ
手探りで行うという
恐ろしいほどの緊張感の中で仕事をしていたと
記憶しています。
※ダークバッグ…カメラがすっぽり入る
光を通さない袋とお考え下さい。
また、このカメラには音声を同時に録音する機能がなく、
音が必要な時は、オープンリールのテープレコーダーを
持って行ったものです。
今では映像と音を同時に撮るのが当たり前の時代ですが
こんな時代もあったのです。