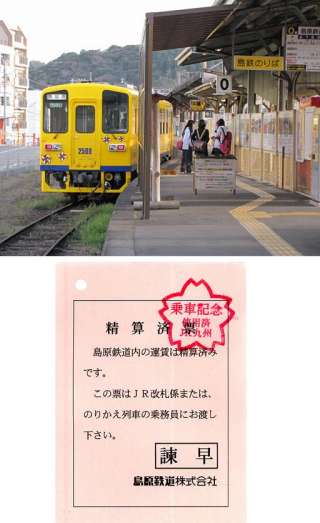2012年09月29日 20時53分
一昨日、昨日とブログの更新をお休みしました。
沖縄・那覇に水曜日から出張があり今回はUPをギブアップしました。
で、昨日(9月28日)仕事が夕方に終わり、本音としては一泊して今日(9月29日)帰るつもりでした。が、台風17号の接近で今日の那覇空港発着便は早々に全便欠航が決まってしまい、なおかつ日曜日(9月30日)は、名古屋を台風が通過する予報も出ていたので、最悪の事態を避けるため何とか金曜日中に帰ろうとしても時間的に間に合う便は満席だし・・・と思っていたら、JAL(JTA)が19:50発の臨時便を飛ばすということで何とかそれに搭乗することができました。
なお、この情報は同行の方が偶然見つけて教えてくれたもので、それがなければこのブログも那覇のホテルで書いているはずでした。こうして今、名古屋にいることでもう年内の「運」は使い果たした気がしています。
さて本題ですが、那覇空港で時間が少しできたので、とりあえず日本最南端の駅、ゆいレール「赤嶺」駅(だけ)を目指しました。乗車したのは「那覇空港」発17:44で「赤嶺」着17:47。そして駅前(本当に目の前)にある『日本最南端の駅モニュメント』に行こうとしたのですが、台風接近により強まっていた“風雨”のため、ずぶ濡れになるのは覚悟すれば済むのですがカメラが危ないと思い断念し、コンコースの顔出し看板で『良し』としました。ニュースで那覇の映像が放送されていましたが、被害が最少で済んでいることを祈るばかりです。
※ゆいレールは平成16年5月15日に乗車しています。(『ゆいレール』の開通は平成15年8月10日)
(忙中閑あり)
懇親会で出かけた沖縄料理の店で見つけたその名も「翌ケロGOLD」。ネーミングが強烈で思わず一本買ってしまいました。大きさは高さ10センチにも満たないモノで、琉球大学の研究によるウコン「琉大ゴールド」の生搾りとのことで、味については『ウコン』としておきましょう。私は初めて見ましたが皆さんは如何でしょうか?