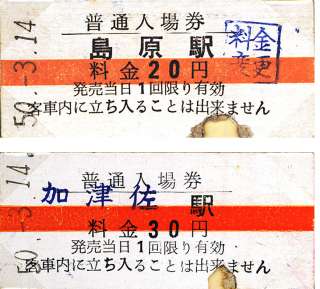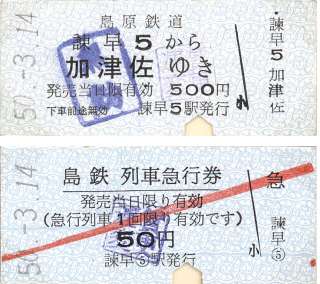2011年05月24日 18時12分

終点の「諫早駅」にもほど近くなった「森山駅」で、私の乗った124レは、
127レ「南島原駅」行きと交換。16:48分着で16:52発と初めて
交換待ち(私の乗車した列車が対向列車待ち)をしました。
さて、こんなに時間を詳しく書けるのは、運転席にあった124レの仕業表を写真に撮っていたからですが、実は、「島原外港駅」でいろいろな写真を撮影したり、列車交換があるたびに乗務員室横の“お立ち台”にいたりしたので、運転士さんからはほぼ全ての撮影が黙認状態となっており、おかげでいろいろな写真を持ち帰ることが出来ました。
●運転席周りの撮影中は、私の撮影が終わるまで乗務員室の外で待っていてくれたほどです。と言う事で、今回は運転士さんへの「声掛け」は敢えてしませんでした。
もっとも私の撮影中、乗客の方は若干、不審な面持ちで見ていたのは
間違いなく、まあ、私は慣れているといえば慣れているのでそれは良しとして、運転士さんの理解はありがたく思いました。
ところで交換した2両編成の先頭車は「2501号」で、
文字通り『キハ2500形』のトップナンバー。それもあってこの写真をUPしました。