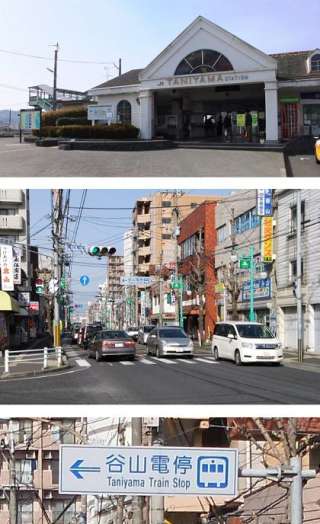2011年04月25日 18時52分

「郡元」停留所にやってきました。
鹿児島市電2大ジャンクションの一つで、位置関係では、
画面手前が「鹿児島中央駅前」方面で、
左側が「交通局前」~「鹿児島駅前」方面。
写真では、右側に分岐する線路も見えていますが、
そちらへ向かうと今、私がやってきた「谷山」方面となっています。
※JR九州「指宿枕崎線」の「郡元駅」とは
どれくらい離れているのでしょうか?
かってこんな事は考えたことも無かったのですが…。
右側の電車は「2111号」で、左側の電車が「9515号」です。
何れも2系統「郡元」~「鹿児島駅前」間の電車です。
この「郡元」での2系統の折り返しは、
「交通局前」方面にある停留所が始終着となっているため、
このような写真がタイミング次第ですが撮れます。
以前は、「谷山」から「西鹿児島駅前(現・鹿児島中央駅前)」方面を
結ぶ電車があったため、右側の分岐線も日常的に使われていました。
と言ってもそれは私の知る“昔”の「鹿児島市電」の時代の更に
“昔”の話しです。
ついでの話し。
「2111号」の右側にある小さな2階建ての小屋のような建物の存在です。
一応、覚えておいてください。