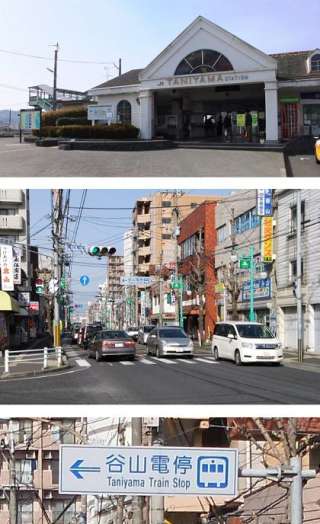2011年04月27日 9時00分

昨年の11月13日に函館市電の「操車塔」の話しをUPしたのですが、
その時、「あそびにん」さんから「高見馬場」と、
もう一つ「郡元」にも“らしき”ものがあるとのコメントを頂いていました。
そこで今回、それを確かめに行ってきました
左側が「高見馬場」で、右側が「郡元」です。
「操車塔」と言えば、左側の「高見馬場」のタイプ、
つまり細い足の様な柱の上に操車作業を行う建屋が乗っかっている
イメージだったのですが、「郡元」のような形態のものを私は初めて見ました。
(「気付きました」が正しいかな?一度来ている訳ですし…)
正直言って、「郡元」のモノは、場所が場所なだけに「操車塔」で
間違いないと思っていますが、あまりにも“常識”と
かけ離れた形態をしており、絶対的な『自信は無い』と
ここに弁明しておきます。
理由は、何せ作業を行う場所の目線が、他の「操車塔」に比べ低いのです。
因みにネットで『「郡元」「操車塔」』で検索したのですが、
かんばしい結果は出ませんでした。
ただ、ここが今も昔も一大ジャンクションであることは間違いなく、
昭和の時代、この地に「操車塔」が無かったということは考えられません。
また、交差点にこのような建物があること自体、
それが「操車塔」である証しとも言えます。
(他の用途を思いつかない…)
よって、前言を撤回し、この2階建ての建物は「操車塔」であるというのが
私の結論です。(「回りくどい」とお叱りを受けそうですね)