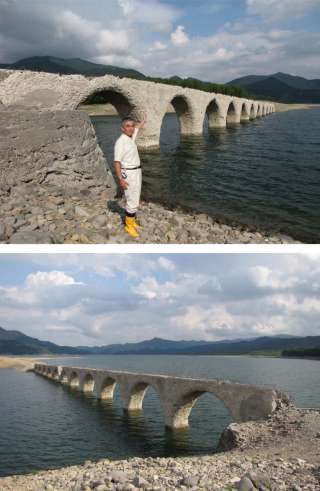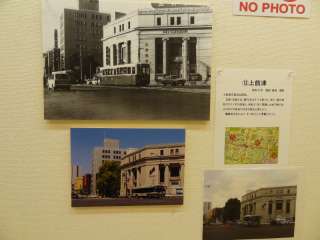2011年09月26日 18時04分
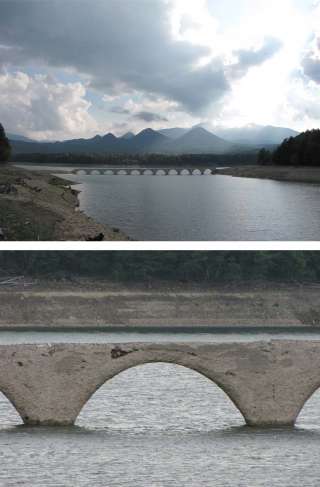
先回までの場所から車で少し奥に入り込み、そこから数分歩いた場所にある
「絶景撮影ポイント」に到着しました。
私がここを訪れた7月13日の水量は、ガイドさんの話しだと
例年より少ないそうで、今年は東日本大震災の影響からか、
水力発電を行っているのではないかと推察されていました。
(ということは、例年ならもっと橋が水没している?)
実際に撮影した感想としては、橋とダム湖の反対側の堰堤との間の
湖面の幅が少し狭いと思っていますが、もう少し時間をかけて場所を探れば
私好みの場所が見つかったのかもしれません。
まあ私一人の撮影行であれば、特に列車の様にシャッターを
押す時間が決まっている訳でもなく、しかも相手は動くわけではないので、
日の差し加減や雲の位置とかの拘りさえ私が持たなければ、
自分の足で高度を調整しながら撮影ポイントを探すのでしょうが、
ツアーと言うこともあり取りあえず『証拠写真』を撮影しました。
※実は、先回の場所もそうですが、撮影だけではなく
その場の雰囲気を楽しむ時間がそこそこあるツアーです。
以上は結果論として、自分が少々納得していないことに対しての言い訳です。
下段写真は、11あるアーチの一つを真正面から捉えてみました。
私はこの写真に湖面を揺らす風の流れを感じています。
皆さんは如何でしょうか?