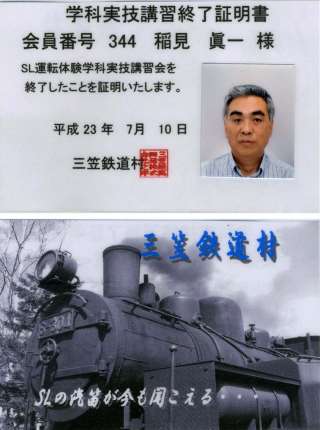2011年08月09日 8時00分

「オホーツク」の車内の人となったあと、
気を取り直して夕食タイムとしました。
車内販売で買ったのが写真のお弁当で「夏のお祭り弁当」(880円)です。
車内販売限定かつ期間限定と言うことで、“限定”というフレーズに弱い
私には、これしか選択肢があり得ませんでした。(積極的に選んだ?)
●「夏のお祭り弁当」とは『夏の風物詩、お祭りをテーマに
北海道の食材を中心に…』との説明書きが同封されていましたが、
ほぼそれを額面通りに受け取っても良さそうな内容でした。
写真の真ん中のブロックは「北海ばら寿し」とのことで、
北海道米の酢めしの上にカニ・ホッキ貝・イクラ・アスパラなどが
トッピングされています。
ここからは写真の大きさと言うより、それぞれの食材が小さい(少ない)ので、
極めて分かりにくいかと思いますが、知床鶏・トキ鮭・帆立等々を
使った北海道の食材が一杯です。
さて、この弁当でお腹は満足したのでしょうか?否!
味はともかく量は少なめのため、
実は、最悪の事態(思うような弁当が購入できない)を想定し、
岩見沢駅の1Fのパン屋さんで予め買っておいたパンを1つ食べました。
(小食の方ならこのお弁当だけでOKかも?)
まあ、「旅気分」を味わうにはこれで十分と言うことで・・・。