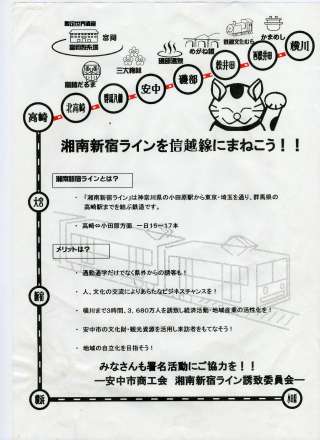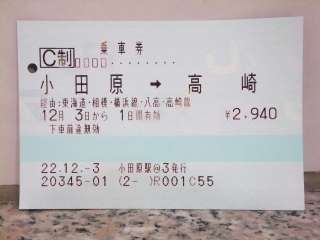2010年12月25日 18時44分

平成22年12月4日、やってきました群馬県安中市の
「碓氷峠鉄道文化むら」。
※写真は、12月5日に撮影したものです。
若桜鉄道のSL『C12 167』、
明知鉄道の『アケチ14号』、
豊橋鉄道東田本線の『3503』と
すっかり「運転」にはまってしまった私も
いよいよ「運転鉄」の“本丸”とも言える
ここの「EF63」に挑戦する日が来ました。
この日は学科講習と実技講習を行い、
本格的な運転体験は翌日以降と言うのは
十分承知はしていたものの、
入り口を通り、碓氷第3橋梁(メガネ橋)を模した
この橋を潜る頃にはもう胸の高鳴りを抑えることが
出来ませんでした。
※決して誇大な表現ではありません。本心です。
集まったのは受講料金3万円也を支払った精鋭10名。
その中に2月26日、このブログの記念すべき
初回に書いた『冬のSLと石炭のマチ・釧路』というツアーに
参加していた方もいらっしゃり、
この“業界”の狭さにまずは驚かされました。
(ツアーの日程…2月19日(金)~21日(日))。