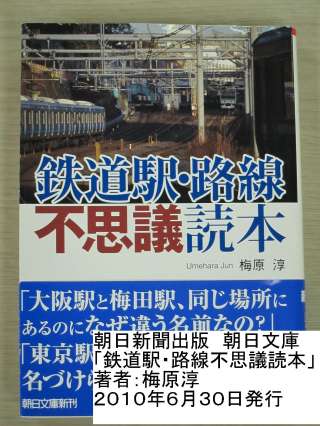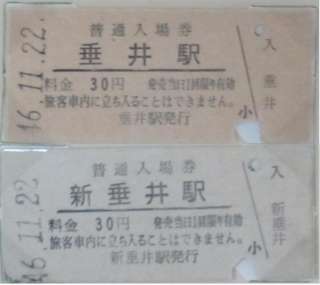2010年08月14日 8時02分

お盆です。皆さん、如何お過ごしでしょうか?
以前、私が番組を制作していた時は、
「24時間テレビ」直前のため、お寺さんにおいでいただく
時間を別にして、家にいたことがあまりありませんが
今はこうしてブログを書いています。
話しを本題に。水谷連絡所での休憩時間の間の午後2時15分、
定期列車が到着しました。
客車3両ながら「立山」のヘッドマークも凛々しく、
正直言って驚きました。
しかも「雑貨列車」ということで運んできた
荷物を降ろし始めたので余計にビックリ。
見ている限り全ての列車にヘッドマークが付くということでは
無いようですが、定期列車には付けているのでしょうか?
何れにしろこの水谷平には、砂防工事に従事する方たちの
宿舎もあるということで
その方たちのための食料等を運んでいるそうです。
さてこの砂防軌道ですが、立山砂防事務所のHPによると
運行区間は「千寿ケ原」(富山地鉄・立山駅近く)~
「水谷」(写真の場所)間、17.7キロ。
軌道連絡所(いわゆる『駅』です)が6か所、
最高時速は上り18キロ、下り15キロ。
※下る列車の方が安全確保のために遅くなっているそうです。
所要時間は1時間45分、この時間をかけて
標高差640メートルを上り下りしています。
最後に軌間は610ミリ。
私の大好物、ナロー中のナローです。